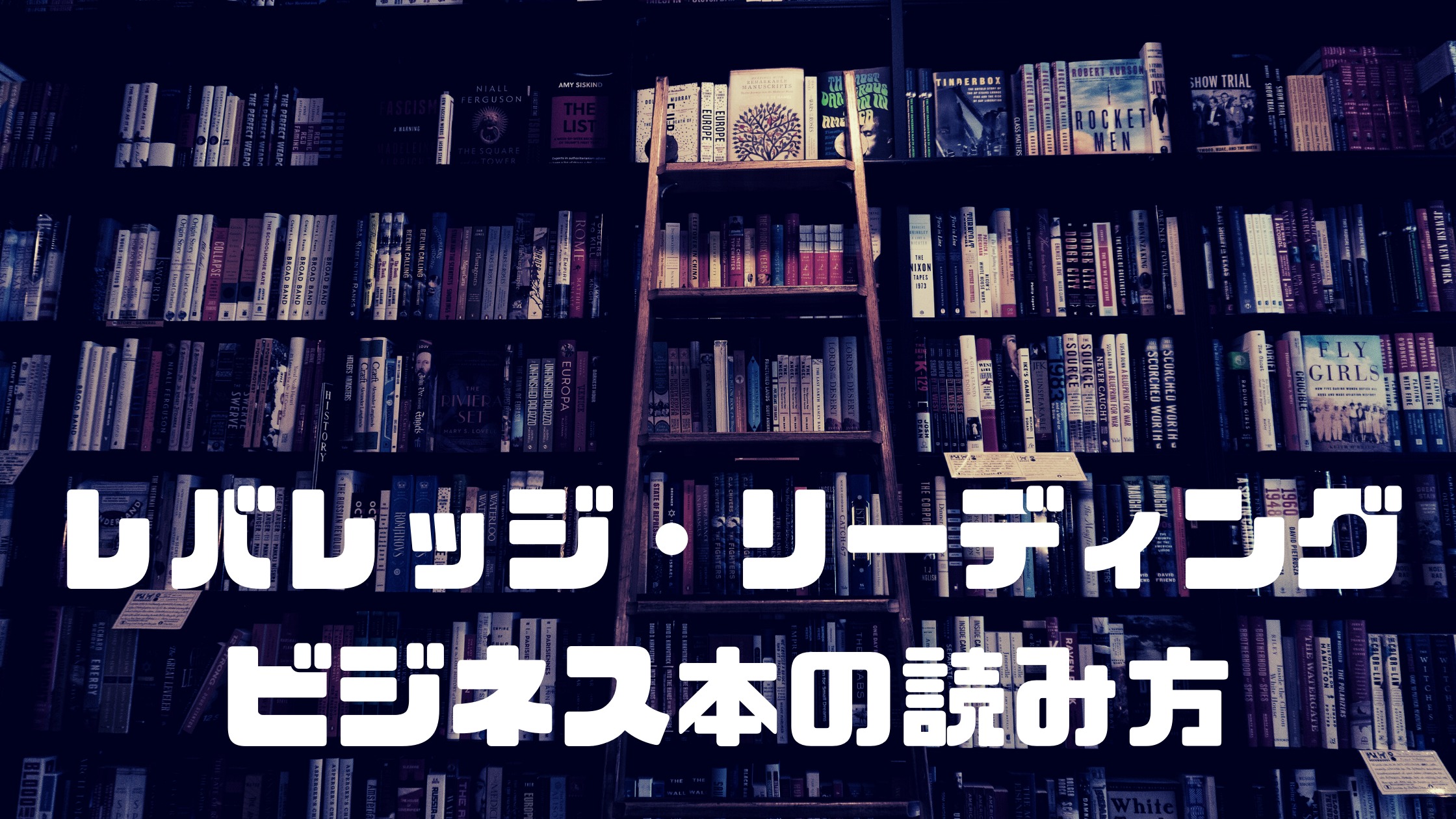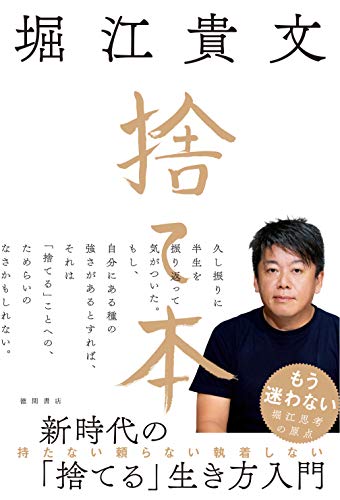何かPythonで面白いものは作れないかと思ったので、
アイデアの思いつき方や形にしていく方法を勉強したく手に取った本、アイデア本のロングセラー
「アイデアのつくり方 / ジェームス W.ヤング」
のまとめです。
この本は
- アイデアとは?
- そのアイデアを出す手順は?
をまとめた本で、厚みはかなり薄くすぐ読み終える事ができる本です。

持ち歩いても邪魔にならないのでお勧め!
アイデアとは?
全く新しいものを生み出すことがアイデアとはこの本では言っていません。
アイデアとは大きく二つ
- 事物の関連性を見つけ出し
- アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせる
これがアイデアと言っています。
ざっくり「携帯電話」+「iPod」=「iPhone」のようなことで、
iPhoneの普及率からその奇抜さ先進さに目を取られますが、源流は既存のモノの組み合わせということです。※ざっくりな例えですよ
アイデアを生み出す手順
以下のフローを守るように示されてます。
ただしどれか中途半端で次に進むと失敗する。
- 資料集め
- 資料に手を加える
- 孵化段階
- アイデアの実際上の誕生
- 現実の有用性に合致させるために最終的にアイデアを具体化し展開させる段階
もう一度大事なことなので書きます。
「どれか中途半端で次に進むと失敗する。」
では次に簡単に各フローを深堀しましょう。
1.資料集め
最もないがしろにされる作業。
ないがしろにされるが故、ほどんどの人がアイデアを手にするまでに挫折する or 次にSTEPに行ってしまう
集める資料は2種類
- 特殊資料
製品とそれを売りたいと想定する人々についての資料
⇒ほとんどが早期に辞めてしまう作業。
しかし諦めずに深く、遠くまで掘り下げるとどんな製品でも消費後の間に
アイデアを生むかもしれない関係の特殊性が見つかる
※Tips:単語帳に特殊資料で得られた事項を一つのカードに記載していく。
そのうち分類/カテゴリ分けが出来るようになる。 - 一般資料
人生にわたり収集し続ける一般知識なもの
⇒これが特殊資料で見つかった特殊な関係と合わさりアイデアに昇華される。
これは人生の中で永遠に続く作業でもある
※新聞の切り抜きのスクラップブックの様に、
自身の体験や新聞の切り抜きなどをノートに纏めて見返す。
するとアイデアの源泉のような機能になる
2.資料に手を加える
資料を集めたら咀嚼のフローに移ります
- 違った角度で見てみたり、二つの事実を並べてみたりどうすれば噛み合うかを調べる。
- こうしていると仮や部分的なアイデアが出てくるので、
不完全でも構わないので単語帳などに書き溜めておく。
3.孵化段階
直接的にはもうなにもしない。
完全にこの問題を心の外に放りだだす。
問題を完全に放棄し、音楽でも映画でも良いので想像力や感情を刺激するものに心を移す。
4.アイデアの実際上の誕生
ふとしたタイミングでアイデアが鮮明に自分の中に入ってくる。
例えば
お風呂で頭を洗っている時とか、
歯磨きしているときにふっとアイデアが降りてくるフローです
5.現実の有用性に合致させるために最終的にアイデアを具体化し展開させる段階
例えるとアイデアは生まれたての子供で、そのままでは潰れてしまう。
なので大事に育ててあげる必要がある。
それには理解ある人々の批判を仰ぐ必要がある。するとアイデアは勝手に育つことが分かる
まとめ
以上がロングセラーの「アイデアのつくり方 / ジェームス W.ヤング」
のまとめです。
- 人生にわたり一般資料や教養を集めつつ、
- 対象のアイデアに合致した特殊資料を限界までかき集め、
- 単語帳でそれらをブレストし、組み合わせを考察し続ける
- ある一点に至ると、すべてを忘れ音楽や映画、趣味に興じる。
- 全てを忘れ、ふとしたきっかけからアイデアが降りてくる。
- 最後にそのアイデアはまだ未熟なので有識者とともにブラッシュアップしアイデアが育つまで練りあげる
短期間でどうにかなる方法ではなく、また突貫で対応できる内容ではありません。
しかし二度とそういった時の苦痛を味わいたくないのであれば、
今の段階で本書を手に取りアイデアを具体化させる訓練を始めてはどうでしょうか?
マインドフルネスやヨガを実施し、前頭葉のトレーニングも効果が期待できるかもしれません